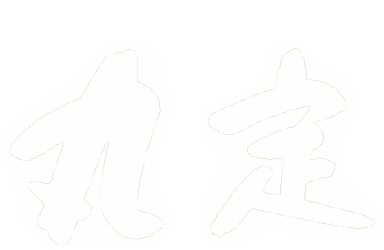丸定旅館の歴史
壺井栄さんの小説「伊勢の的矢の日和山」祖父の墓を訪ねる旅を中心に、伊勢志摩紀行を小説にした作品に丸定旅館の元になる船宿定吉屋が登場します。
小説 伊勢の的矢の日和山

イセのマトヤの ヒヨリヤマ。
この調子をもった言葉は、祖母の歌う子守唄であったと思う。祖母はそれを六十年間、ひとり息子と、やがて次々と生まれた十人の孫たちに語って聞かせたのだ。何百回、何千回、もしかしたらそれ以上くりかえしたかもしれぬ。
――イセのマトヤの ヒヨリヤマ……
そこに自分の夫の墓があるというのだった。夫は江戸通いの船乗りであったのが、船中でコレラにかかって亡くなり、イセのマトヤのヒヨリヤマに墓があるというのである。 ――小(ち)んまい石塔になってな、小豆島勝蔵と刻(ほ)ってあるといや。お前ら、大けになったら、その、じじの墓にまいってくれ。おばあの代わりまいってあげてくれよ。おばあは一生、ようまいってあげなんだ。本意(ほい)ないことじゃった……
こんなふうに語るのだったが、本意ない様子は子供の私たちには感じられず、あまりおもしろくないおとぎばなしでも聞くようにそれを聞いていた。そして、時には祖母をまぜかえすのである。
「お前らのじいさんはな、若い時、船にのっとってな。――」
祖母がそう語り出すと、孫たちはそのあとをひったくって、代わる代わるにいう。

「知っとらあい。コロリで死んだんじゃ」
すると祖母はにこにこして、
「そうそう」
「イセの マトヤの ヒヨリヤマ じゃろう」
「そうそう」
「小(ち)ンまい石塔に、小豆島勝蔵 いうて刻ってあるんじゃろう」
「そうじゃ、そうじゃ」
「おばあは、よう墓まいりせいで、ほいないことじゃったん」
「そうとも、そうとも」
「大けになったらおばあの代わりに、まいってくれいうんじゃろう」
「そうとも、そうとも」
「いせまいりのついでに、墓まいりするんじゃ、のう」

伊勢まいりのついでにでもと遠慮っばくいっていたところが、田舎の貧しい百姓女の一生けんめいさであったのも、子供の私たちにはわからなかった。
半世紀も昔のことである。海越え山越え、はるばると小豆島から伊勢への旅は、あだやおろそかではない。
伊勢講にでもあたって伊勢へまいる幸運も十人の孫の中にひとりあるかないか知れたものではない時代のことだ。
そしてその通り十人の孫たちは長い間伊勢に無縁で過ごしたのであった。
私がはじめてそれを思い立ったのは、祖母のその悲願を小説に書き、ふところに少しばかりのゆとりができたときだった。
おじいさんの墓まいりにいこうと思うと語ると、私の姉はそれを父の墓まいりととりちがえて、「もう、十三年かしら?」

とおどろいた。父がなくなって十年目くらいのことだった。
「イセの マトヤの ヒヨリヤマのおじいさんよ」
私がそういうと、中絶していた記憶を大急ぎでたぐりよせるように、ああ、ああと嘆声をあげながら、
「イセのうんうん、マトヤの、そうそう、ヒヨリヤマ!」
そして腹をかかえて笑った。
私はひとりで旅立った。十三年前のことになる。私が伊勢の的矢の日和山という文字を地図の上でさがしだしたのは小学校の六年の時だった。おとぎばなしだと思っていた祖母の話に真実性を感じ、私は地図を祖母につきつけて、的矢の説明をした。その時に祖母の悲願は私の心の奥にひきつがれたのかもしれぬ。私は地図を便りに的矢をたずねた。日和山は墓地のある丘であった。霰(あられ)のふる中で小さな石塔をのぞいて回ったがわからなかった。禅法寺という寺を訪ねると過去帖をみせてくれたが、一日一回の船の時間にせき立てられて、見当たらぬまま、祖母ではないが本意(ほい)なくも帰途につかねばならなかった。戦時中のこととて、泊まる宿も心にまかせなかった。
その本意なさが、私をふたたびそこへ運んだのだ、昭和二十九年の秋である。旅立つ前に、私は息子の研造――といっても末妹の生んだ子供であるが――にむかって、
「イセの マトヤの ヒヨリヤマって知ってるかい」
「しってるよ。おかあさんの小説にある」
「そうだ、そうだ。そこへいくんだがね。お前、ついていく気あるかね」
すると彼の目は急に輝き出し、
「本当っ、おかあさん、本当につれてってくれるの」
「ほんとさ」
「バンチョ バンチョ。ぼく、伊勢神宮をいっぺん見たかったんだよ」
建築家の卵である芸大生の研造はそういう見地からもわくつきだした。やれネクタイだ、やれワイシャツだ、といそいそしだした。それを眺めて私はひそかにおもしろがっていた。小豆島勝蔵のひ孫は小(ち)ンまい石碑をみつけてどんな感情をもたらすだろうということについてであった。勝蔵氏と研造では百歳の時代の差がある。乳呑児をひとり抱えて夫にとり残された祖母の、苦労の果てのあきらめと、子守唄やおとぎばなしにまで昇華した悲願を、この息子はどう理解しようとするだろうか。
宿は宇治山田から十里ばかりはなれた賢島の志摩観光ホテルであった。そこでおちあうことにして、私は息子に一日おくれで出かけた。友人の紹介だったせいか、ホテルに着くと支配人は丁重な態度で、
「お部星は、陛下のお泊まりになった洋室をとってございますが……」
私は即座に願いさげて和室をえらび、すぐ息子をよんだ。もう夜だった。とんできた息子は、一足先の実地見聞に興奮して多弁になり、しかしあとは小声で、
「でもね、食事のとき、まごついたよ。こんなんだもん」
と、手まねでナイフやホークの並んださまを示し、
「たった一日でお箸に郷愁を感じたよ」
田舎育ちの彼には、あまり経験のないことだったのだ。そのくせ私が「陛下の部屋」のことを話すと二十歳の息子はすぐ心を動かし、
「おかあさん、そこ、ぼくはだめ?」
「よせよせ、ひいじいさんの墓まいりじゃないか。あんまりそれるなよ」
ひいじいさんといったあとで私はふっと気がついておかしくなった。私の祖父とはいえ、勝蔵氏は三十歳にみたぬ若さで一生を終わったのだ。その若さが祖母の心にいつまでも生きていたらしく、祖母はときどき、じいさんとは呼ばずに、勝つぁんと、まるで恋人の名でも口にするようにいった。それは八十五歳でなくなるまで時々祖母の口から洩れた。祖父のことを語るとき、祖母の心はいつも初々しい若妻だったにちがいない。祖母は八十五になるまで男ざかりのままの夫の姿をしっかり胸にいだいていたのだ。それを語る祖母の目はいつもかがやき、その声は若かった。それだけに、私は祖母がいとしくてならない。私は祖母の代わりに、伊勢まいりのついででなく祖父の墓をたずねたかった。
私たちは遊覧船をやとって的矢湾を渡った。
「海のハイヤー・ラッキー号」は、ラジオまで備えつけた快速船である。青い海の色は瀬戸内海と似ている。しかしここは真珠の海なのだ。養殖真珠のいかだが、いたるところに組まれている。そしてこの海は日本一の牡蠣どころでもあるという。養殖の牡蠣もいたるところ浮標(ブイ)をただよわせて真珠と競っているようだ。

――祖父は、牡蠣を食いすぎてコレラになったのではあるまいか……
そんなことがふっと私の心をよぎる。しかし私はそのことは口には出さず、息子をふりかえった。
「おじいさんの時代は、えっちら ぎっちらと、艪(ろ)をこいでいたんだね」
「うん」
「帆まかせ、風まかせで、小豆島から江戸へ往復するには、ずいぶん日数がかかったろうな」
船乗りの妻の心細さを、一世紀むかしに逆のぼって私は味わっていた。その時と同じ風が私の頬をなで髪を乱している。ラッキー号の乗組員は三十前後の男だった。いろいろと案内をしてくれる洋服を着たその男にも私は祖父をかぎだそうとしていた。私は無遠慮に、彼ら船乗りの収入をきいた。
「だいたい八千から、一万位ですな。家では百姓もしていますから、それで結構食っていけますね」
私の頭にふと一つのことが思い出された――さいら(サンマ)六寸、まんじ(まんじゅう)は二文――というのだ。むかしからさんまは六寸、まんじゅうは二文と相場が決まっていたのに、まんじゅうが五厘になったといって祖母は嘆声をもらしたことがある。百年後の今はまんじゅうは十円として、五千倍である。その勘定でゆくと、祖父の給金は一円五十銭か二円になる。それで妻子を養い、時化(しけ)で港へ寄れば遊びもしたのだ。
「あ、船宿(ふなやど)というのが、今もありますかしら」
思いついて聞くと、若い船乗りは我意を得たように、
「あります、あります。私の親類ですから、それではそこへ船をつけましょう」

船宿、定吉屋と板壁にじかに書いた家の下に船をつけると、彼は小さな桟橋をまっ先にかけ上がり、赤ん坊をだいて出てきた若い女に、
「おじいさんいるかい」
「芋ほりにいっとる」
くしゃくしゃと話しあっていると思うと、若い女がかけ出していった。いもほりのおじいさんを畑へよびにいってくれたのだ。その間、私たちは船宿の天井の低い二階の部星に通された。おじいさんは腰をかがめて走るようにして帰ってきた。孫らしい使の女にあらましを聞いたらしく、
「ようおいでなさりました」
とあいさつをした。しぼんで小さくなったような八十に近そうな老人であった。雑念を払いおとし、善意だけが永生きしているような、やわらかな目をしていた。私は並んで日和山への坂道を上がりながら、
「小豆島の船なんですけどね。私のおじいさんがそれに乗っていて、ここの港で亡くなりましてね。そのお墓が、日和山にありますので」
「はあ、はあ。船乗りさんも、ようけ亡くなりましてな、たいてい私にわかると思いますが、いつごろのことですかいな」
「それがね、はっきりしないんですよ。だいたい明治のはじめごろか、ちょっと前ぐらいと思いますが」
「それじゃあ、わかりませんな。私が生まれんさきじゃから」
「一度、調べにきましたけど、船の時間がぎりぎりで、よく調べずに帰ったんですよ。禅法寺さんで過去帳を見せてもらいましてね」
「あ、さよで、そんならもいっべん見せてもらいますか。――しかし遠いとこのお方は墓まいりもなかなかのことでございましてな、まつるお方もない墓は、せんど、まとめてしまいましてな。そのお墓で供養塔を、こしらえましてな。それの中にあるかもしれませんな」
墓地は小高い丘の上にあった。
「あれですわ」
と、そのセメントでかためた墓の集団を指しながら、しかしなおなにかを求めるように、
「小豆島、勝蔵といいましたかいな」
と、道ばたの草むらをかきわけてのぞいてみるのだった。枯れた草の中に小さな墓がいくつもかくれていた。いかにもそれは旅ではかなく消えた人たちの仮の墓らしいものだった。残された人たちのささやかな手向けは、苔むしているのだ。供養塔は戒名を刻んだ墓石の表をみせて、円錐状鍾にセメントでかためてある。慈海玄航海士、真珠道珠信士、月海慈舟、海安浮舟、仙海貞金、海岳智月、繁海良昌、ああ、なんとたくさんの海の犠牲者たちであろう。十五人亡者とあるのは難破全滅した船の人たちであろう。
「これはみな、船でなくなったのですか」
海という字の戒名をみて私がいうと、老人は曲がった腰に片手をあてて円錐の塔をふり仰ぎながら、
「みんなでもございませんが、海の人が多うござりますな。的矢は昔から避難港でしてな、海が荒れますとここに船が寄ってきよります。航海中病人が出ましても、この港にきて、養生しますし、そんなことで、諸国のお方のお墓がよけいにありましてな」
私は途中の道ばたで摘んだ野花の花束を作り、諸国の船乗りたちに捧げた。おそらく墓石の裏に刻まれてあるらしい小豆島勝蔵の文字は、セメントにぬりこめられて見つけるよしもなかった。それをもう残念にも思わない私になっていた。
これだけの船の人たちといっしょに眠っている祖父を、あわれとは思えない。ただそれを一度も見ることのなかった祖母にだけ思いは走った。供養塔は楠らしい、大木の繁みの下にあった。そのわきの椿のむらがった下を螺旋(らせん)なりに登る小道があった。それに従ってゆくと、墓地よりも一つ小高い見晴しの平地に出た。畳なら十枚は敷けないせまい場所である。まん中に日時計があり、風が少し強い。
「ここが日和山と申しましてな、船乗りさんはここへきて沖をながめて、あしたの日和を見るんですわ。それで日和山、いいますのですな」
そういって額に手をかざし、沖をながめる老人の姿に、私は祖父を見る思いをした。船宿定吉屋は古い宿だという。私の祖父たちは、この老人の親の代に、ここで航海の中休みをして米や野菜を買いこみ、水をもらっていたのだろう。
老人は、私の問いに答えて「今でも小豆島のたまり(醤油)船は時々寄ります。家へ帰って帳めん調べたらなに丸かわかります」
そして思いつめたように、
「せっかくお出でたんや。お寺さんに経(きょう)あげてもらいますか。そんなら一走り先に行って、いうてきます」

老人は小走りに墓地を出ていった。しかしなかなか戻ってこなかった。待ちくたびれて息子を迎えに出すと、老人はひとり寺の縁に腰かけていたという。とって返した息子は、くつくつ笑いながら、
「お寺の坊さんも、いもほりに行って留守なんだって、それで、畑へ使いを出してもらって、待ってるんだって」
「おやおや。きょうは的矢村のいもほりを二軒も邪魔したね」
やがて野良着を衣にかえたらしい坊さんといっしょに船頭のおじいさんもやってきた。南国らしい強い日射しに汗をかいている。坊さんは十三年前のことを覚えていて、過去帳の中に小豆島勝蔵の見つかったことを語った。しかし墓そのものはやはり供養塔の中にぬりこめられたものの一つであるらしい。坊さんはもってきた小さな卒塔婆を供養塔にまつり、経をあげた。
――勝蔵じいさん、おばあの代わりに、孫とひ孫がまいったぞえ。いせまいりのついででなく、ここへわざわざまいったぞえ……
無言の言葉をおくりながら、私は、神妙に手を合わせている四代目の息子ののびた背丈を眺めた。はじめて新調した背広をきて、胸ポケットに赤い飾りハンカチがのぞいている。私は祖父の血をひく四代目の息子の、そのきざっぽいおしゃれをさえ許す気になっていた。
私のそんな感傷におかまいなく、息子のほうはこのあとひとりで伊勢まいりをするという。それもよかろう。
昭和30年発行「婦人画報・お正月号(新年号)」より引用。